ラウィーニア – 2009/11/13 アーシュラ・K・ル=グウィン (著), 谷垣 暁美 (翻訳)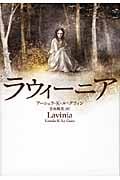
「ラウィーニア 著:アーシュラ・K・ル=グウィン 訳:谷垣暁美」を読んでみた。
ラウィーニアとは叙事詩『アエネーイス』に出てくる女性の名前。トロイア戦争の英雄アエネーアスの妻の名前。
さて、なんのことやらさっぱり……と思ってあとがきを読むと、トロイの木馬の戦争で負けて逃げ出したアエネーアスが妻を得るまでの話とあった。
トロイの木馬……やっと理解できそうな単語が出てきた。詳しくないけど、戦争で木馬のなかに忍びこんで敵陣に入り込んだエピソードは知ってる。あの辺りの話なのねと思いながら、読むことにした。
でも、この物語面白いのは『詩人ウェルギリウス』が物語の中のキャラクターとして出て来ること。ウェルギリウスとは『アエネーイス』を書いた人。彼は自分が書いた詩の中のキャラクターと出会うことになっている。そして、未来をラウィーニアに語る。
ラウィーニアはその運命を受け入れて、詩人が語った通りの未来を歩む。語られたのはアエネーアスが死ぬまで。その先はどうなるんだ……と思ったけど、その後もアエネーアスの前妻の息子アスカニウスが色々と事件を起こしてる。アスカニウスの話はゲドっぽいなとも思う。父親を越えられないと思い込むのとか、傲慢さなんかがゲドの雰囲気がある。ただ、ゲドと違ってアスカニウスには義弟(ラウィーニアの息子)シルウィウスがいる。義弟君は母親の手の中でぬくぬく育っていて、憎らしいという気持ちも混ざるので、さらに複雑。
そして、さらりと混ざり込む同性愛。ああ。この時代は同性愛は普通だったんだっけ、でも唐突過ぎてどういうこと??と思ってしまった。同性愛が普通であっても、王として世継ぎは必須で、王妃とはご無沙汰って……アスカニウスの人物像は中々に複雑で面白かった。
他にもラウィーニアの母親のアマータ。息子たちがみんな亡くなって、少しおかしくなってしまってラウィーニアにつらく当たる。けれど、甥のトゥルヌスとラウィーニアを結婚させようと画策して、戦の扉を開き、その戦でトゥルヌスが死んでしまうと自ら死を選ぶ。と、このキャラも中々に強烈。
ラウィーニアの友のシルウィアは牧畜を生業にしている家の子で、王の娘であるラウィーニアとは格が合わないけれど、ずっと仲良くしていた。けれど、ラウィーニアがシルウィアの兄のアルモを結婚相手に選ばないことを知ってからは会うことがなくなる。この時代だからなのか、平和だからなのか『王』と『農民』がこんなに近いんだなぁと思った。近いけど、分かり合うことはない。仲良くしていた友がいなくなるけど、代わりに奴隷のマルーナとは一生を共にする。マルーナはラウィーニアの儀式の手伝いをしたり、結婚後もラウィーニアのやっていた儀式を引き継いだりと、中々に重要な役どころ。王家に近いからこそ弁えていて、全てを話せる親友ではないけれど、一番近い存在になる。
こういう文化が垣間見えるのも楽しい。儀式もわかりやすく書かれていた。こういう文化はがっつり調べて書いてあるんだろうな。でも、やっぱり『奴隷』というものが理解できてないと思う。この時代の『奴隷』は敗戦国(戦に負けた部族なども含めて)から連れてきた人たちなので、一応『戦』という儀式めいたものはあるんだよな。西洋人がアフリカに対してやったような強制誘拐とは違う……。
でも、日本にはそう言う文化があったわけではない(と思う。聞いたことがない)からか、いまいちつかめないなぁと思いながら読むことになる。知識としては理解できるけど、どんな立ち位置で、どういう価値観の元に労働してるのかなと。。特にこういう王族に仕えた奴隷……がよくわからない。
日本だと、それなりの家柄の婦女子だったよね。江戸時代の大奥なんかの影響かな。そういうものという感覚があるせいで、『奴隷が王族に使える』というのが本当にわかんないんだよな。
ちゃんとトロイの辺りの神話を他の本で読んでみようかなと思ってしまった。
アエネーアスが最後、フクロウになってるのも、読んでいて圧巻だった。その視点で書かれていたのかと思ってしまった。そして、鳴きかわすフクロウって……。最後にさらりと回収していく伏線がすごいな。やたらとフクロウが出てくるけど、それが『ラウィーニア』だからだと最後でわかる。
気になったところ。
『わたしたちが怖がったのは狼や猪であり、人間ではなかった。わたしの子ども時代を通して、このような秩序が保たれていたので、わたしは世の中というものは常にこんなふうだったのであり、これからもずっとそうなのだと思い込んでいた』45p
これ、最初読んだときはわからなかったけど、最後まで読むと先代の王たちが亡くなった後は治安が悪くなって、『女子供が一人で出歩けない』状態にまでなっているということなんだなと思った。つまり、ラウィーニアの父親はすごい王様だった……。
『ラウィーニア、わたしはきみを正当に扱わなかったのかもしれない』58p
詩人がラウィーニアに言う言葉。ここでの『正当』がよくわからない。物語の本筋とは少しずれているから、出てくる場面が少ないとかそういうもの? 大元の神話を読まないと、わからないのかな。男女差別だった……というものでもなさそうな感じなのだけど。
『わたしが女を代表して男に対する憤りを表明する語り手であると、あなたがたは思っているかもしれないが、その期待には沿えない。(略)私は正義に憧れる。だが、正義とは何なのか知らない。』95p
この辺りはあとがきでも書いてあったけど、女性の立場の弱さは描かれてるけど、別に男性と対立してはいない。そして、そういう物語でもない。男には男の苦悩があって、女には女の苦労がある。そういうもの『全部』を書いてしまいたいだけなのかなと思ってるけど、この解釈もまた違うのかも。
『「若い男に、無私無欲を求めるのは難しいよ」愁いを含んだ笑みを浮かべて、アエネーアスは言う。
「若い女にそれを期待するのは、ありがちなことだけど」とわたし。』163p
この辺りのちくりとしたやり取りも面白い。男性には男性の世界しか見えなくて、女性には女性の世界しか見えてない。だから、話は少しずれたり平行線だけど、これも前後を読むと別に『怒り』があるわけではない。こういうものだよねっていう話。
『妻になったわたしは、かつて感じていた悲しい怒りを決して感じることがなかった。(略)わたしたち女は自分の生活を、あり方を変えられる。自分の意思とは関係なく、気がつけば変化している。』241p
この辺り、ある意味では心理だけど、だから『変えるのは女の役目』になってる部分もあるんだろうなと思う。この物語がただ事実を書いてあるだけだとしても、なんていうかこの部分はモヤっとしてしまった。
『「知恵も、戦闘での武勇と同じく、ひとつのウィルトゥースですよね?」
「でも、知恵は、男だけがもつウィルトゥースではないと思うわ」と私が言った。』282p
ウィルトゥースとは美徳のこと。男だけがそれを持っていると言ったアスカニウスにラウィーニアが「そうじゃない」と答えたシーン。
アスカニウスの尊大さだけど、トロイア人(アスカニウス)たちは女性がそんな風に男性と同じ立場で言葉を発しないという文化差がある……らしい。でも、これに限らず、男は『男だけがそれを持つ』と思ってるものはたくさんありそうだけど。
やっぱりアスカニウスが一番、いい役どころだなぁと思う。
物語は面白かった。ごちそうさまでした。
『ラウィーニア』
アーシュラ・K・ル=グウィン作品の他の感想
「どこからも彼方にある国」を読んで
「闇の左手」を読んで
「絵本「いちばん美しいクモの巣」を読んで
「ギフト」を読んで
「ヴォイス」を読んで
「パワー」を読んで 「影との戦い ゲド戦記Ⅰ」を読んで
「空飛び猫 空飛び猫シリーズ1」を読んで
「ラウィーニア」を読んで

